
(1) 相談・発見
- 保護者・親族から児童相談所への相談
- 学校や医療機関からの通告・相談
- 近隣住民からの通告・相談
- 警察での保護
日本語 / ENGLISH
保護者のいない児童や、保護者がいても何らかの理由で育てることが困難な児童など、保護や養育を必要とする子どもに対し、行政の責任で保護・養育を行うしくみを、「社会的養護」と言います。
このページでは、社会的養護について皆さまに知っていただきたいことをまとめました。
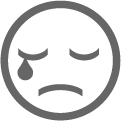
子ども虐待
身体的な虐待や性的虐待はもちろん、心理的虐待、育児放棄(ネグレクト)も子ども虐待に含まれます。虐待の背景には、親の健康問題、経済的な不安定さ、孤立など、さまざまな社会的要因が隠れているかもしれません。

健康上の問題
内臓疾患などのいわゆる「肉体の病気」はもちろんのこと、うつ病や統合失調症、アルコール依存などの精神科疾患も、親の健康問題に含まれます。失業したりして、子育てに影響します。

経済的な問題
親の失業や不安定な雇用によって、子育てが難しくなることがあります。これに関連して、近年「子どもの貧困」(子育て世帯の相対的貧困率の上昇)が注目されています。
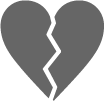
離婚・DV
ひとり親になることで、収入を確保しながら子育ての負担もすべて引き受けることになります。また、子どもの面前で行われるドメスティック・ヴァイオレンス(DV)は、心理的虐待にあたります。
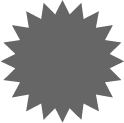
事件・事故
交通事故や事件、火災など、突発的な事故に巻き込まれることによって、子育てが困難な状況になることがあります。仮に保険金が下りても、養育する人がいないと、子育てはできません。

自然災害
子どもが災害孤児になり、親族等が代わりに子育てを引き受けられない場合があります。生活再建の負担から子育てができなくなる場合もあります。
さまざまな事情から保護者による養育が難しくなったとき、あるいはそのおそれがあるとき、子どもを守り育てる責任が行政(国・自治体)にあります。そのための一連のしくみが「社会的養護」です。社会的養護は「子どもの最善の利益のために」、「社会全体で子どもを育む」という理念を掲げ、以下のような幅広い役割を担うことになっています。
虐待などを受けるなど、適切な養育が受けられなかった場合、子どもは心に傷を負ったり、発達にゆがみや遅れが生じたりします。社会的養護では、これらを癒し、回復させ、適切な発達を図ります。精神科医や臨床心理士などの専門家が関与します。

(1) 相談・発見
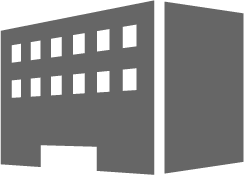
(2) 一時保護
児童相談所(児相)が子どもの状況を確認し、必要に応じて「一時保護所」で保護します。子どもの状況を調べ、在宅のまま子どもを支援できないか検討します。保護者が養育を続けるべきではないと判断した場合、児童養護施設に入所させるなどの「措置」を決定します。

(3) 措置先へ
子どもが児童養護施設・里親などでの生活を始めます。施設の空き状況などの事情から、子どもが全く知らない土地に移るケースもあります。
<代替養育>
子を親から分離して、施設や他の家庭で養育します。分離の必要性は児童相談所が判断し(児童福祉法第27条)、家庭裁判所の承認があれば、必ずしも親の同意を必要としません(同第28条)。また、分離の期間は家庭状況に応じて判断され、一時的な場合もあれば、措置上限の18歳まで続く場合もあります。
<その他の養育支援>
子を保護者から分離せず、在宅や通所、一時的入所を通して子育て支援をします。母子生活支援施設とショートステイ以外は、児童相談所が措置先・措置内容を決めることができます。
児童相談所における
児童虐待の相談件数
出典:厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「社会的養育の推進に向けて」平成29年12月 ( リンク )
※福祉行政報告例を集計したもの。
※平成22年度の件数は、福島県を除いた数。
子ども虐待の定義
18歳に満たない子どもに対して保護者が行う以下の行為が、「児童虐待」に該当します。
身体的虐待 | 殴る、蹴る、たたく、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など |
|---|---|
心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス)、きょうだいに虐待行為を行う など |
性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など |
ネグレクト | 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など |
出典:厚生労働省「児童虐待の定義と現状」( リンク )
※「児童虐待の防止等に関する法律」第2条で、児童虐待の法律上の定義がなされています。
※児童虐待の定義にある「保護者」には、親権者(父母等)の他に、未成年後見人や、児童養護施設長・里親も含まれます。
虐待かなと思ったら…
オレンジリボン運動について
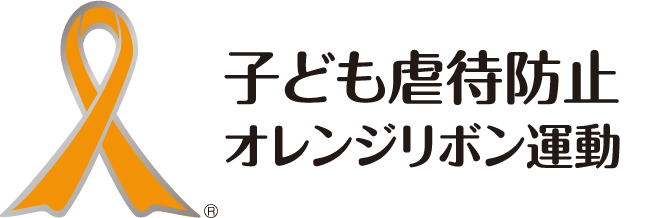
「オレンジリボン運動」は、子ども虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。
私たち特定非営利活動法人ライツオン・チルドレンも、子ども虐待防止オレンジリボン運動に参加しています。
出典:認定特定非営利活動法人 児童虐待防止全国ネットワーク「オレンジリボンについて」( リンク )
※「オレンジリボンマーク」は、認定特定非営利活動法人 児童虐待防止全国ネットワーク の登録商標です。
(このページの記載内容は、2018年5月6日に更新されました)
Copyright 2014-2024 特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン